本編を視聴するには、会員登録の上購入が必要です
第10回「近藤勇・先を越された甲府入城」
幕末、池田屋事件をはじめ、京都の治安維持などで活躍した新撰組の局長・近藤勇の敗北を紐解き、今を生きる私たちにとっても役立つ教訓を探る。
旧幕府軍が鳥羽・伏見の戦いに敗れ、江戸に敗走した後、勇は江戸に進軍する新政府軍を迎え撃つべく甲府城を目指す。しかし、板垣退助率いる新政府軍が一足早く甲府入城を果たし、勇は戊辰戦争の一つ、甲州勝沼の戦いで敗北を喫する。
勇はなぜ新政府軍より早く甲府城を押さえることができなかったのか?
関連動画
偉人・敗北からの教訓
すべて見る-

第53回「前田慶次・出奔を選んだ天下御免の傾奇者」
新着無料 -

第52回「聖徳太子・アジアの超大国との外交交渉」
無料 -

第51回「渋沢栄一・挫折だらけの実業界の父」
2024.07.29 22:00 配信終了
無料 -

第50回「徳川秀忠・関ヶ原遅参と大坂の陣」
-

第49回「シリーズ秀吉③ 九州攻めと島津義久」
-

第48回「シリーズ秀吉② 四国攻めと長宗我部元親」
-

第47回「シリーズ秀吉① 高松城水攻めと毛利輝元」
-

第46回「シリーズ家康③ 家康と嫡男・信康の切腹」
-

第45回「シリーズ家康② 家康と信長との同盟」
-

第44回「シリーズ家康① 家康と三河一向一揆」
-

第43回「シリーズ信長③ 信長と足利義昭・擁立した将軍の追放」
-

第42回「シリーズ信長② 信長と武田信玄・突然の裏切り」
-
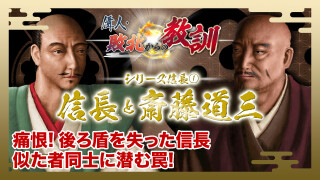
第41回「シリーズ信長① 信長と斎藤道三・同盟の行方」
-
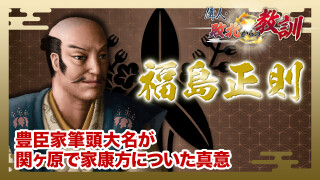
第40回「福島正則・豊臣家を守れなかった猛将」
-

第39回「織田三兄弟・天下を継げなかった息子たち」
-

第38回「松永久秀・信長に反旗を翻した名将の実像」
-

第37回「上杉景勝・北の関ヶ原での撤退戦」
-

第36回「大塩平八郎・世直しを目指した過激な戦い」
-

第35回「荒木村重・信長に反旗を翻した籠城戦」
-

第34回「武田信玄・名補佐役を亡くした悲劇」
-

第33回「白虎隊・会津に散った若く尊き命」
-
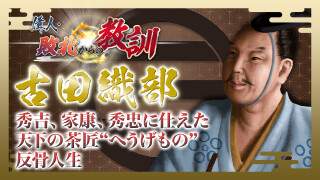
第32回「古田織部・家康の逆鱗に触れた大名茶人」
-
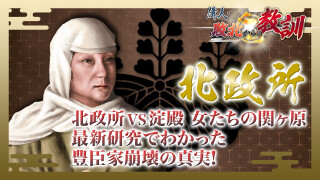
第31回「北政所・悲しき豊臣家臣団の分裂」
-

第30回「小早川秀秋・想定外の『裏切り者』の汚名」
-
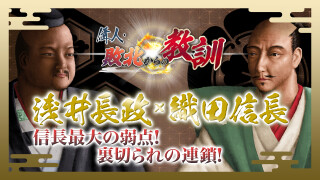
第29回「織田信長と浅井長政・義兄弟の悲しき戦い」
-

第28回「千利休・天下一となった茶人の運命」
-

第27回「新田義貞・忠義を貫いた名将の悲劇
-

第26回「楠木正成・無謀な戦いに挑んだ忠臣」
-

第25回「毛利輝元・破られた家康との約束」
-

第24回「豊臣秀吉・夢破れた大陸進出」
-

第23回「徳川綱吉・赤穂事件の裁きをめぐる失敗」
-

第22回「徳川家康の決断・ライバル秀吉への臣従」
-
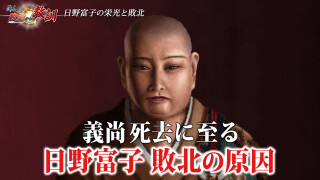
第21回「日野富子・若き息子の死と悲しみ」
-
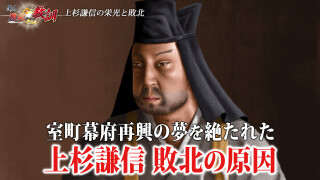
第20回「上杉謙信・果たせなかった室町幕府再興」
-
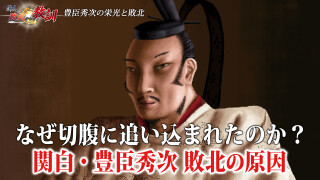
第19回「豊臣秀次・天下人になり損ねた関白」
-

第18回「北条政子・守れなかった家族の命」
-
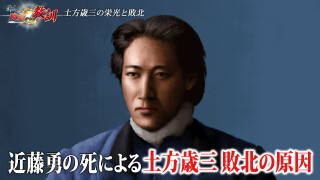
第17回「土方歳三・叶わなかった盟友の生存」
-
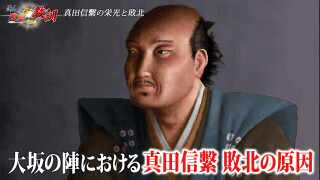
第16回「真田信繁・貫き通した豊臣家への忠誠」
-
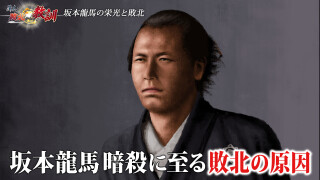
第15回「坂本龍馬・危険人物と見なされた理由」
-

第14回「伊達政宗・夢と散った百万石大名」
-
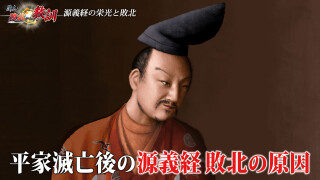
第13回「源義経・悲劇を招いた兄弟の対立」
-

第12回「淀殿・豊臣家の滅亡を引き寄せた決断」
-
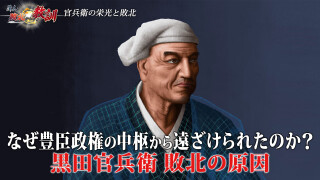
第11回「黒田官兵衛・出世の道を閉ざされた切れ者」
-
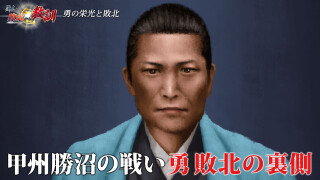
第10回「近藤勇・先を越された甲府入城」
-

第9回「西郷隆盛・明治政府との無謀な戦い」
-

第8回「北条氏政・小田原攻めに至る秀吉との攻防」
-

第7回「柴田勝家・賤ヶ岳の明暗を分けた秀吉との差」
-

第6回「今川義元・想定外の桶狭間」
-
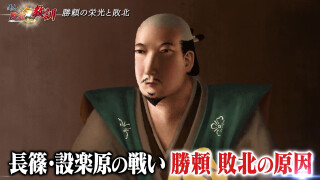
第5回「武田勝頼 長篠・設楽原での過ち」
-
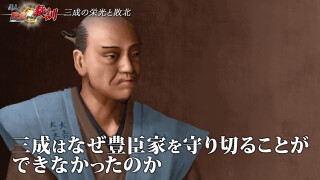
第4回「石田三成・関ヶ原大敗の真相」



