報道ライブ インサイドOUT 第1・第3金曜版
9月19日(金)「資本主義は限界なのか?「脱成長」のシナリオとは?」
ゲスト:斎藤 幸平(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)
第2次世界大戦終結から80年、世界経済はグローバル化の流れの中、成長、拡大の道を進んできた。それは、人、モノ、カネが国境を越えて往来することで、多様な価値観や利便性、豊かさを社会にもたらした。しかし、同時に、新たな分断や格差の拡大を生んできたのも事実であり、近年、その弊害は顕在化しつつある。気候変動による自然災害の多発、大規模化、ロシアによるウクライナ侵攻が国際秩序の破壊、"アメリカ・ファースト"を掲げるトランプ大統領の再登板に象徴される分断深刻化。このような現象は、グローバル資本主義が限界に達しつつある表れなのだろうか?
グローバル資本主義に起因する様々な弊害を、どのように乗り越えていけばよいのか?その解として、ベストセラー『人新世の資本論』の著者である斎藤幸平氏は、共産主義の父=マルクスを"読み直し"、新たな解釈を与えることで「脱成長」のシナリオを唱える。しかし、既に20世紀において失敗の烙印を押された「社会主義・共産主義」に、その答えが本当に読み取れるのだろうか?番組では、当の齋藤氏をゲストに迎え、マルクスの新たな解釈で"資本主義の矛盾"を克服することができるのか、問います!
エピソード

2月6日(金)「2026衆院選 争点はココだ!減税と財政政策」
ゲスト:片岡 剛士(PwCコンサルティング チーフエコノミスト)、熊野 英生(第一生命経済研究所 首席エコノミスト)※オンライン出演
衆議院総選挙に向けた各党の争点について検証するシリーズ、最終日のテーマは「消費税減税と財政政策」。各党は物価高対策として消費税減税を公約に掲げたが、減税に消極的と見られてきた自民党が食料品の消費税率ゼロを掲げたため、各党が消費税減税を競う形に。ただし、党ごとに主張は異なり、実現に向けての課題は多い。特に問題となるのが税収減を補うための財源で、各党はそれぞれ見立てを公表しているが、具体的な提案には乏しい。仮に消費税減税が行われることになれば、成長分野への投資のための財源が削られてしまう事態も考えられる。さらに、財政規律に対する金融市場からの信頼が失われ、さらなる円安や金利上昇を招く恐れも。消費税減税の実施が現実味を帯びる中、増大する防衛費はどう確保するのか。高市総理が立ち上げた日本成長戦略会議の委員を務め、積極財政派の片岡剛士氏と、日本銀行出身で消費税減税に慎重な立場をとる熊野英生氏、二人のエコノミストとともに成長戦略を考える。
ゲスト:片岡 剛士(PwCコンサルティング チーフエコノミスト)、熊野 英生(第一生命経済研究所 首席エコノミスト)※オンライン出演
衆議院総選挙に向けた各党の争点について検証するシリーズ、最終日のテーマは「消費税減税と財政政策」。各党は物価高対策として消費税減税を公約に掲げたが、減税に消極的と見られてきた自民党が食料品の消費税率ゼロを掲げたため、各党が消費税減税を競う形に。ただし、党ごとに主張は異なり、実現に向けての課題は多い。特に問題となるのが税収減を補うための財源で、各党はそれぞれ見立てを公表しているが、具体的な提案には乏しい。仮に消費税減税が行われることになれば、成長分野への投資のための財源が削られてしまう事態も考えられる。さらに、財政規律に対する金融市場からの信頼が失われ、さらなる円安や金利上昇を招く恐れも。消費税減税の実施が現実味を帯びる中、増大する防衛費はどう確保するのか。高市総理が立ち上げた日本成長戦略会議の委員を務め、積極財政派の片岡剛士氏と、日本銀行出身で消費税減税に慎重な立場をとる熊野英生氏、二人のエコノミストとともに成長戦略を考える。
無料

1月16日(金) 「"トランプ版モンロー主義"から見る2026米中動向」
ゲスト:小西 克哉(国際ジャーナリスト)、富坂 聰(拓殖大学海外事情研究所 教授)
世界を震撼させた米軍のベネズエラ攻撃。作戦成功を伝える会見でトランプ大統領は、西半球を重視する姿勢と"トランプ版モンロー主義(ドンロー主義)"という思想に言及した。これはグローバル覇権からの撤退なのか、具体的な戦略は? 米政府は先月「国家安全保障戦略」を公表、西半球重視やモンロー主義への回帰を打ち出した。文書は中国についても言及しているが、直接非難するような文言は見当たらない。米国は対中戦略を転換したのだろうか。一方、非「西半球」の中国はこうした動きをどう受け止めているのだろうか。激動の国際情勢とともに幕を開けた2026年。就任以来、台風の目であり続ける米・トランプ政権と、中国・習近平政権に挟まれた日本の活路は? 国際ジャーナリストの小西克哉氏、拓殖大学の富坂聰氏とともに考える。
ゲスト:小西 克哉(国際ジャーナリスト)、富坂 聰(拓殖大学海外事情研究所 教授)
世界を震撼させた米軍のベネズエラ攻撃。作戦成功を伝える会見でトランプ大統領は、西半球を重視する姿勢と"トランプ版モンロー主義(ドンロー主義)"という思想に言及した。これはグローバル覇権からの撤退なのか、具体的な戦略は? 米政府は先月「国家安全保障戦略」を公表、西半球重視やモンロー主義への回帰を打ち出した。文書は中国についても言及しているが、直接非難するような文言は見当たらない。米国は対中戦略を転換したのだろうか。一方、非「西半球」の中国はこうした動きをどう受け止めているのだろうか。激動の国際情勢とともに幕を開けた2026年。就任以来、台風の目であり続ける米・トランプ政権と、中国・習近平政権に挟まれた日本の活路は? 国際ジャーナリストの小西克哉氏、拓殖大学の富坂聰氏とともに考える。
無料

12月19日(金)「どう実現?高市政権『責任ある積極財政』」
ゲスト:永濱 利廣(経済財政諮問会議民間議員 / 第一生命経済研究所 主席エコノミスト)
高市首相の総理就任後初となる、今年度の補正予算が国会で成立した。この予算には、高市政権が掲げる総合経済政策が反映されているわけだが、その基本方針を議論する場が内閣府の経済財政諮問会議だ。高市首相を議長に、日銀総裁や経済閣僚などで構成され、予算編成の方針となる「骨太の方針」をまとめあげる。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」では、財政規律に配慮しつつ成長への投資を行い「強い経済」を目指すという。しかし、長期金利の上昇や円安の進行、また物価高対策などいくつもの課題がある中、どのような形で実現していくのか。また、債務残高が増え続ける中でのさらなる積極財政出動は、財政健全化を遠ざけることにはならないのか。
番組では高市首相の積極財政を2週連続で特集。高市政権はどのような成長戦略を描き、日本経済を回復させようとしているのか。2回目の今回は、経済財政諮問会議に民間議員のひとりである長濱利廣氏をゲストに、「内側」から、高市政権の経済政策と「責任ある積極財政」について聞く。
ゲスト:永濱 利廣(経済財政諮問会議民間議員 / 第一生命経済研究所 主席エコノミスト)
高市首相の総理就任後初となる、今年度の補正予算が国会で成立した。この予算には、高市政権が掲げる総合経済政策が反映されているわけだが、その基本方針を議論する場が内閣府の経済財政諮問会議だ。高市首相を議長に、日銀総裁や経済閣僚などで構成され、予算編成の方針となる「骨太の方針」をまとめあげる。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」では、財政規律に配慮しつつ成長への投資を行い「強い経済」を目指すという。しかし、長期金利の上昇や円安の進行、また物価高対策などいくつもの課題がある中、どのような形で実現していくのか。また、債務残高が増え続ける中でのさらなる積極財政出動は、財政健全化を遠ざけることにはならないのか。
番組では高市首相の積極財政を2週連続で特集。高市政権はどのような成長戦略を描き、日本経済を回復させようとしているのか。2回目の今回は、経済財政諮問会議に民間議員のひとりである長濱利廣氏をゲストに、「内側」から、高市政権の経済政策と「責任ある積極財政」について聞く。
無料

12月12日(金) 「妙薬か?劇薬か?高市政権『責任ある積極財政』の行く先・その①」
ゲスト:河村 小百合(日本総研 調査部 主席研究員)
日本初の女性総理、高市早苗氏の総理就任から53日。極めて高い支持率のもと高市首相は、コロナ禍後最大となる巨額の補正予算を組んだ。この大規模な財政支出に対しては、首相は「責任ある積極財政」をうたい「財政の持続可能性を確保した形だ」というが、果たしてどういうことなのか?「責任ある積極財政」の核となるのは、経済対策として打ち出した危機管理投資・成長投資による「強い経済」。岸田・石破時代の財政健全化路線を脱し、経済成長のための国力強化に重きを置く。その方針は内閣府が主管する会議体のメンバーにも表れているという。積極的な財政出動を支持する"リフレ派"の布陣が描く、日本経済復活の戦略とは。
番組では高市首相の積極財政を2週連続で特集。1週目の今回は、財政規律を重視する河村小百合氏を迎える。現政権を金融市場はどう評価しているのか、膨れ上がる赤字国債の先には何が待っているのか。そして、いまの日本財政に足りないモノを考える。
ゲスト:河村 小百合(日本総研 調査部 主席研究員)
日本初の女性総理、高市早苗氏の総理就任から53日。極めて高い支持率のもと高市首相は、コロナ禍後最大となる巨額の補正予算を組んだ。この大規模な財政支出に対しては、首相は「責任ある積極財政」をうたい「財政の持続可能性を確保した形だ」というが、果たしてどういうことなのか?「責任ある積極財政」の核となるのは、経済対策として打ち出した危機管理投資・成長投資による「強い経済」。岸田・石破時代の財政健全化路線を脱し、経済成長のための国力強化に重きを置く。その方針は内閣府が主管する会議体のメンバーにも表れているという。積極的な財政出動を支持する"リフレ派"の布陣が描く、日本経済復活の戦略とは。
番組では高市首相の積極財政を2週連続で特集。1週目の今回は、財政規律を重視する河村小百合氏を迎える。現政権を金融市場はどう評価しているのか、膨れ上がる赤字国債の先には何が待っているのか。そして、いまの日本財政に足りないモノを考える。
無料
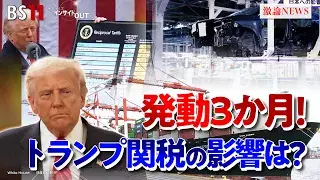
11月21日(金)「トランプ関税発動から3か月 日本経済への影響は」
ゲスト:中西 孝樹(ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト)、松浦 大将(みずほリサーチ&テクノロジーズ シニア米国経済エコノミスト)
発動から3か月が経ったトランプ関税。相互関税と自動車関税の税率は一時より下げられたものの、全体的には大幅な引き上げとなった。先日発表された7~9月のGDPは、6四半期ぶりのマイナス成長となり、関税の影響の大きさが改めて浮き彫りになった。巨額の対米投資の合意と合わせて、日本への現実的な影響は。日本の基幹産業である自動車産業も、トランプ関税の影響を大きく受けたが、その度合いはメーカーによってまちまちだった。何が明暗を分けたのか。今後も関税の影響が続くと見込まれる中、各社はどんな戦略で立ち向かうのか。関税によって強い国内経済を目指すというトランプ政権だが、その思惑は実現できるのか。また、それに対して日本はどう対応していくべきなのか。
ゲストに、長年自動車産業の調査に携わってきた中西孝樹氏と、米国経済の調査を行うエコノミスト松浦大将氏を迎え、トランプ関税本格化後の世界について考える。
ゲスト:中西 孝樹(ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト)、松浦 大将(みずほリサーチ&テクノロジーズ シニア米国経済エコノミスト)
発動から3か月が経ったトランプ関税。相互関税と自動車関税の税率は一時より下げられたものの、全体的には大幅な引き上げとなった。先日発表された7~9月のGDPは、6四半期ぶりのマイナス成長となり、関税の影響の大きさが改めて浮き彫りになった。巨額の対米投資の合意と合わせて、日本への現実的な影響は。日本の基幹産業である自動車産業も、トランプ関税の影響を大きく受けたが、その度合いはメーカーによってまちまちだった。何が明暗を分けたのか。今後も関税の影響が続くと見込まれる中、各社はどんな戦略で立ち向かうのか。関税によって強い国内経済を目指すというトランプ政権だが、その思惑は実現できるのか。また、それに対して日本はどう対応していくべきなのか。
ゲストに、長年自動車産業の調査に携わってきた中西孝樹氏と、米国経済の調査を行うエコノミスト松浦大将氏を迎え、トランプ関税本格化後の世界について考える。
無料
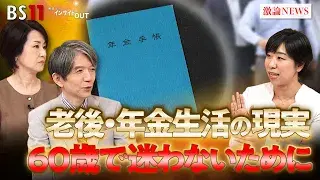
11月7日(金)「老後生活の現実とは?60歳で迷わないために」
ゲスト:塚越 菜々子(ファイナンシャルプランナー)
深刻な人手不足にインフレという経済情勢も相まって、働く高齢者は年々増加し、65~69歳の2人に1人は就業者となっている。老化防止や健康目的という声もあるが、一方で、生活費を工面する必要に迫られるケースもある。老後生活の柱である「年金」だけにたよった生活は難しいのだろうか。公的年金制度を巡っては「年金制度改正法」が6月に成立。注目されたのは「年収106万円の壁」撤廃だったが、厚生年金適用事業所の拡大や、在職老齢年金の基準額引き上げなど、老後生活に関わる調整も多い。しかし、その内容は複雑に入り組み、はたして改善になるのか?改悪になるのか?判別は難しい。実際、何がトクなのか?どこに気を付けるべきなのか?
番組では、収入に応じた年金額を試算し、繰り上げ受給といったオプションによって受給額がどう変化するのかを解説。ゲストに「保険を売らないファイナンシャルプランナー」塚越菜々子氏を迎え、安心できる老後を送るための"コツ"を聞く。
ゲスト:塚越 菜々子(ファイナンシャルプランナー)
深刻な人手不足にインフレという経済情勢も相まって、働く高齢者は年々増加し、65~69歳の2人に1人は就業者となっている。老化防止や健康目的という声もあるが、一方で、生活費を工面する必要に迫られるケースもある。老後生活の柱である「年金」だけにたよった生活は難しいのだろうか。公的年金制度を巡っては「年金制度改正法」が6月に成立。注目されたのは「年収106万円の壁」撤廃だったが、厚生年金適用事業所の拡大や、在職老齢年金の基準額引き上げなど、老後生活に関わる調整も多い。しかし、その内容は複雑に入り組み、はたして改善になるのか?改悪になるのか?判別は難しい。実際、何がトクなのか?どこに気を付けるべきなのか?
番組では、収入に応じた年金額を試算し、繰り上げ受給といったオプションによって受給額がどう変化するのかを解説。ゲストに「保険を売らないファイナンシャルプランナー」塚越菜々子氏を迎え、安心できる老後を送るための"コツ"を聞く。
無料

10月17日(金)「どうなる新政権 日本政治の行方は?」
ゲスト:中北 浩爾(中央大学教授)、鈴木 哲夫(ジャーナリスト)
石破総理の辞任の意向を受けて行われた、自民党総裁選。高市氏が女性初の総裁に就任も、その直後に長年連立政権を組んでいた公明党が離脱を発表。さらに苦しい立場に追い込まれた"少数与党"自民党。党の内部では一体何が起きているのか。来週21日には臨時国会が召集。そこで行われる首相指名選挙に向け、立憲民主党など野党3党は首相候補の一本化に向けた調整を行うなど、各党の駆け引きは激しさを増している。高市氏が首相となることができるのか、もしくは政権交代の実現性は? 自民と野党連合どちらが政権を獲得しても、不安定な政権運営は避けられない。さらに多党化が進む中、政策合意はますます困難に。混迷が続く日本の政治にはどんな未来が?
現代日本政治論が専門の中北浩爾氏、長年永田町の裏側を取材してきたジャーナリストの鈴木哲夫氏とともに考える。
ゲスト:中北 浩爾(中央大学教授)、鈴木 哲夫(ジャーナリスト)
石破総理の辞任の意向を受けて行われた、自民党総裁選。高市氏が女性初の総裁に就任も、その直後に長年連立政権を組んでいた公明党が離脱を発表。さらに苦しい立場に追い込まれた"少数与党"自民党。党の内部では一体何が起きているのか。来週21日には臨時国会が召集。そこで行われる首相指名選挙に向け、立憲民主党など野党3党は首相候補の一本化に向けた調整を行うなど、各党の駆け引きは激しさを増している。高市氏が首相となることができるのか、もしくは政権交代の実現性は? 自民と野党連合どちらが政権を獲得しても、不安定な政権運営は避けられない。さらに多党化が進む中、政策合意はますます困難に。混迷が続く日本の政治にはどんな未来が?
現代日本政治論が専門の中北浩爾氏、長年永田町の裏側を取材してきたジャーナリストの鈴木哲夫氏とともに考える。
無料

10月3日(金)「総裁選終盤情勢 / 滞る再開発 いま駅前で何が起こっているのか?」
ゲスト:鈴木 哲夫(ジャーナリスト)、牧野 知弘(オラガ総研代表 / 不動産事業プロデューサー)
全国の都市で進む駅前の再開発。特に東京を中心とした大都市では、「100年に一度」と言われる大ブームだったが、その動きに陰りが見え始めている。相次ぐ再開発の中止や見直しの裏には、一体何が起きているのか。また、タワーマンションをはじめとする不動産価格の高騰はとどまることを知らず、実際の需要とかけ離れたマネーゲームの材料にされる懸念も。不動産価格の上昇が、富裕層と持たざるもののさらなる格差を招く一因とも指摘されている。さらに、再開発の頓挫によるマンション供給の停滞は、「住宅難民」の増加につながるのか?
再開発で変わりゆく街並みとともに、人々の生活も変化する中、今後の不動産のあり方を、大手デベロッパーと大手コンサル勤務を経て、不動産プロデュースを行う牧野知弘氏とともに考える。
ゲスト:鈴木 哲夫(ジャーナリスト)、牧野 知弘(オラガ総研代表 / 不動産事業プロデューサー)
全国の都市で進む駅前の再開発。特に東京を中心とした大都市では、「100年に一度」と言われる大ブームだったが、その動きに陰りが見え始めている。相次ぐ再開発の中止や見直しの裏には、一体何が起きているのか。また、タワーマンションをはじめとする不動産価格の高騰はとどまることを知らず、実際の需要とかけ離れたマネーゲームの材料にされる懸念も。不動産価格の上昇が、富裕層と持たざるもののさらなる格差を招く一因とも指摘されている。さらに、再開発の頓挫によるマンション供給の停滞は、「住宅難民」の増加につながるのか?
再開発で変わりゆく街並みとともに、人々の生活も変化する中、今後の不動産のあり方を、大手デベロッパーと大手コンサル勤務を経て、不動産プロデュースを行う牧野知弘氏とともに考える。
無料

9月19日(金)「資本主義は限界なのか?「脱成長」のシナリオとは?」
ゲスト:斎藤 幸平(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)
第2次世界大戦終結から80年、世界経済はグローバル化の流れの中、成長、拡大の道を進んできた。それは、人、モノ、カネが国境を越えて往来することで、多様な価値観や利便性、豊かさを社会にもたらした。しかし、同時に、新たな分断や格差の拡大を生んできたのも事実であり、近年、その弊害は顕在化しつつある。気候変動による自然災害の多発、大規模化、ロシアによるウクライナ侵攻が国際秩序の破壊、"アメリカ・ファースト"を掲げるトランプ大統領の再登板に象徴される分断深刻化。このような現象は、グローバル資本主義が限界に達しつつある表れなのだろうか?
グローバル資本主義に起因する様々な弊害を、どのように乗り越えていけばよいのか?その解として、ベストセラー『人新世の資本論』の著者である斎藤幸平氏は、共産主義の父=マルクスを"読み直し"、新たな解釈を与えることで「脱成長」のシナリオを唱える。しかし、既に20世紀において失敗の烙印を押された「社会主義・共産主義」に、その答えが本当に読み取れるのだろうか?番組では、当の齋藤氏をゲストに迎え、マルクスの新たな解釈で"資本主義の矛盾"を克服することができるのか、問います!
ゲスト:斎藤 幸平(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)
第2次世界大戦終結から80年、世界経済はグローバル化の流れの中、成長、拡大の道を進んできた。それは、人、モノ、カネが国境を越えて往来することで、多様な価値観や利便性、豊かさを社会にもたらした。しかし、同時に、新たな分断や格差の拡大を生んできたのも事実であり、近年、その弊害は顕在化しつつある。気候変動による自然災害の多発、大規模化、ロシアによるウクライナ侵攻が国際秩序の破壊、"アメリカ・ファースト"を掲げるトランプ大統領の再登板に象徴される分断深刻化。このような現象は、グローバル資本主義が限界に達しつつある表れなのだろうか?
グローバル資本主義に起因する様々な弊害を、どのように乗り越えていけばよいのか?その解として、ベストセラー『人新世の資本論』の著者である斎藤幸平氏は、共産主義の父=マルクスを"読み直し"、新たな解釈を与えることで「脱成長」のシナリオを唱える。しかし、既に20世紀において失敗の烙印を押された「社会主義・共産主義」に、その答えが本当に読み取れるのだろうか?番組では、当の齋藤氏をゲストに迎え、マルクスの新たな解釈で"資本主義の矛盾"を克服することができるのか、問います!
無料
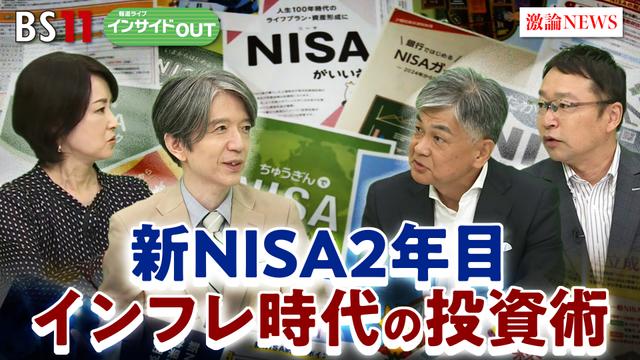
9月5日(金)「新NISA2年目!インフレ時代の投資術」
ゲスト:井出 真吾様(ニッセイ基礎研究所 チーフ株式ストラテジスト)、代田 秀雄様(三菱UFJアセットマネジメント 特別業務顧問)
去年1月にスタートした新NISA制度では「年間投資枠の拡大」「保有期間が無期限に延長」など、より投資しやすい環境に。物価上昇が続くなか「貯蓄から投資へ」の流れは着実に広がり、NISA口座数は2600万を突破、これまで投資を考えなかった人々に門戸を開く契機となった。新たに「オルカン」や「S&P500」をはじめとする投資信託商品も登場。長く投資市場に関わってきた専門家が、以前は考えられないような「低コスト」を実現していると指摘する。では実際に投資するなら、どのような考えのもと投資に臨むべきなのか?
番組では、ニッセイ基礎研究所の井出真吾氏と「オルカン」の生みの親である代田秀雄氏を招き、自身が実践する資産運用の組み合わせ方(ポートフォリオ)を大公開!NISA初心者はもちろん、既に運用を始めている人も、プロの投資戦術を学べる絶好の機会だ。
ゲスト:井出 真吾様(ニッセイ基礎研究所 チーフ株式ストラテジスト)、代田 秀雄様(三菱UFJアセットマネジメント 特別業務顧問)
去年1月にスタートした新NISA制度では「年間投資枠の拡大」「保有期間が無期限に延長」など、より投資しやすい環境に。物価上昇が続くなか「貯蓄から投資へ」の流れは着実に広がり、NISA口座数は2600万を突破、これまで投資を考えなかった人々に門戸を開く契機となった。新たに「オルカン」や「S&P500」をはじめとする投資信託商品も登場。長く投資市場に関わってきた専門家が、以前は考えられないような「低コスト」を実現していると指摘する。では実際に投資するなら、どのような考えのもと投資に臨むべきなのか?
番組では、ニッセイ基礎研究所の井出真吾氏と「オルカン」の生みの親である代田秀雄氏を招き、自身が実践する資産運用の組み合わせ方(ポートフォリオ)を大公開!NISA初心者はもちろん、既に運用を始めている人も、プロの投資戦術を学べる絶好の機会だ。
無料